Home > フランス料理それは一つのフロンティア > Menu アイーダ[副題:ビクトリア時代の栄光](その構想) > Menu アイーダ[副題:ビクトリア時代の栄光](実際のお料理)
Home > フランス料理それは一つのフロンティア > Menu アイーダ[副題:ビクトリア時代の栄光](その構想) > Menu アイーダ[副題:ビクトリア時代の栄光](実際のお料理)
Menu アイーダ[副題:ビクトリア時代の栄光](実際のお料理)@ A ta guele
トウモロコシのパリソワール仕立て:Soupe de mais en Paris-soir et blinis de mais avec caviar de maison


牡蠣のソースアルベール:Huitre sauce Albert


バルケット ヴィクトリア:Barquette Victoira




こっ……これは……ブルトン???
ハサミが!!生きてる!!!


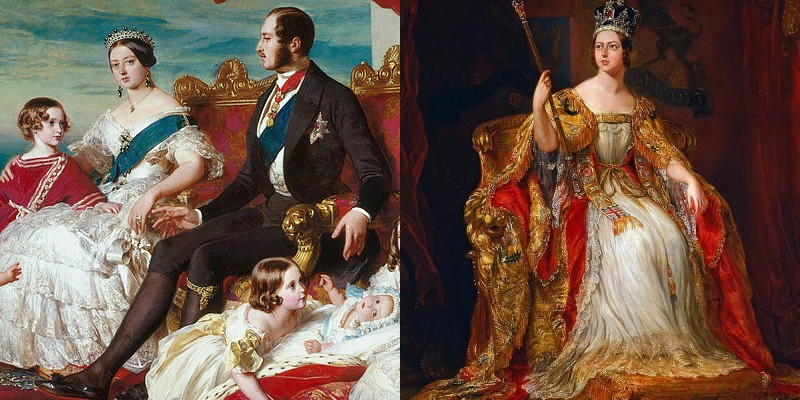
アイーダ:Aida turobot


フランス料理をして、まさに【世界之歴史】を語らしむ。
【メニュー】は、ひとつの”演劇的空間”と言う舞台でもある。。


お口直しのグラニテ:granite aux melon



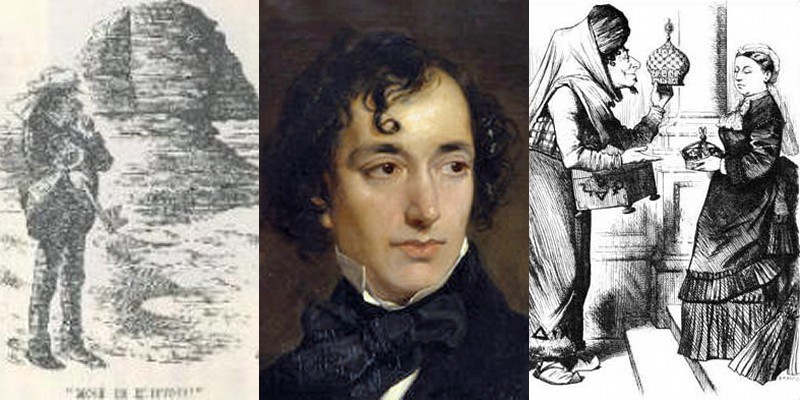




スフレ ロチルド:Souffle Rothscjild

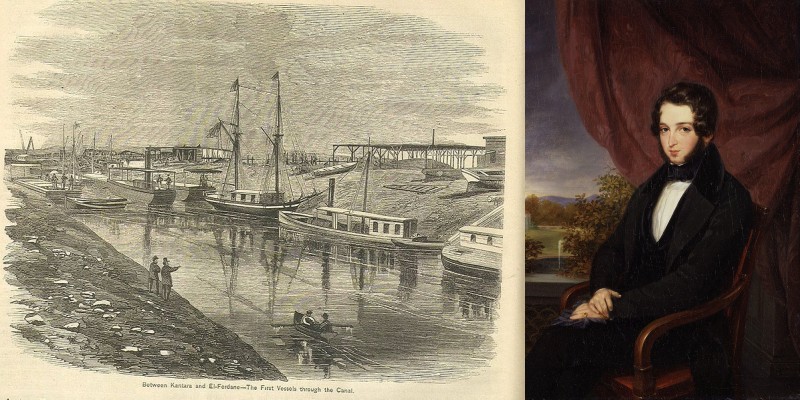


食後のプティフールとコーヒー


【太陽の沈まぬ国欧羅巴】は、ディズレーリとビスマルクの【勢力均衡(バランスオブパワー)】による【平和】の賜物